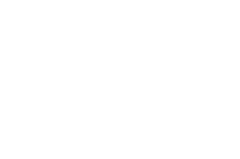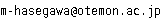■ 一般向け情報
研究ジャンル : 生活経営
研究のキーワード : 環境、地域、食、経済、経営、持続可能性
研究に関するコメント : 1.家計の消費構造、2.地域生活の質、3.消費者の環境配慮行動、4.企業の環境配慮活動、5.自然環境・社会環境と食文化の関連、などのテーマについて、定量的・定性的両方のアプローチで研究しています。
|
|
■ 学歴
|
■ 職歴
|
1.
|
2013/04~2017/03
|
京都大学 森里海連環学教育ユニット 研究員
|
|
2.
|
2014/04~2018/03
|
神戸国際大学 経済学部 非常勤講師
|
|
3.
|
2016/04~2018/03
|
奈良女子大学 文学部 非常勤講師
|
|
4.
|
2017/04~
|
奈良女子大学 生活環境学部 非常勤講師
|
|
5.
|
2017/04~2018/03
|
筑紫女学園大学 現代社会学部 専任講師
|
|
6.
|
2018/04~
|
追手門学院大学 経済学部 経済学科 講師
|
|
■ 著書・論文歴
|
■ 現在の専門分野
|
環境政策、環境配慮型社会, 家政学、生活科学, 地域研究, 経済政策, 商学 (キーワード:消費生活、消費者行動論、社会的責任、持続可能発展、環境経済、地域活性化、食文化)
|
|
■ 所属学会
|
1.
|
2016/04~
|
日本家政学会
|
|
2.
|
2014/06~
|
日本経営診断学会
|
|
3.
|
2019/03~2020/09
|
∟ 関西部会幹事
|
|
4.
|
2019/10~2020/09
|
∟ 第53回全国大会実行委員会委員長
|
|
5.
|
2020/10~2024/09
|
∟ 大会運営委員会委員
|
|
6.
|
2020/10~2024/09
|
∟ 理事
|
|
7.
|
2022/02~2022/09
|
∟ 関西部会 部会長代行
|
|
8.
|
2022/10~2024/09
|
∟ 関西部会 部会長
|
|
9.
|
2010/05~
|
環境情報科学センター
|
|
■ 学会発表
|
■ 教育上の能力
|
■ 研究課題・受託研究・科研費
|
■ 講師・講演
|
■ 社会における活動
|
1.
|
2024/07~2025/03
|
茨木市総合計画審議会委員
|
|
2.
|
2022/10~2024/09
|
日本経営診断学会関西部会部会長
|
|
3.
|
2022/05~2023/03
|
大阪府総合的な交通のあり方検討に関する有識者懇話会委員
|
|
4.
|
2022/02~2022/09
|
日本経営診断学会関西部会部会長代行
|
|
5.
|
2021/05~
|
茨木市都市計画審議会委員
|
|
6.
|
2020/10~
|
泉大津市環境保全審議会委員
|
|
7.
|
2020/10~2024/09
|
日本経営診断学会大会運営委員会委員
|
|
8.
|
2019/12~2023/12
|
大阪府国土利用計画審議会委員
|
|
9.
|
2019/12~2023/12
|
大阪府都市計画審議会委員
|
|
10.
|
2019/10~2020/09
|
日本経営診断学会第53回全国大会実行委員会委員長
|
|
11.
|
2018/12~2022/11
|
大阪府大規模小売店舗立地審議会委員
|
|
■ 委員会・協会等
|
■ 学内職務
|
|
1.
|
2018/04~2020/03
|
FD推進委員
|
|
2.
|
2018/04~2021/03
|
図書館委員
|
|
3.
|
2018/04~
|
入学式、卒業式
|
|
4.
|
2018/04~2021/03
|
入試広報委員
|
|
5.
|
2019/04~2021/03
|
経済学会・研究会委員
|
|
6.
|
2021/04~2024/03
|
経済学部内教務担当
|
|
7.
|
2024/04~
|
WIL推進センター委員
|
|
■ 教育、研究、社会貢献活動の方針
|
1.
|
【教育活動の方針】 現代は、変化の速い時代である。未来は、いっそう速くなるかもしれない。そうした中で生きていくためには、何かを学び続ける姿勢とそれを実行できる能力が必要である。学ぶことの楽しさを伝えることで、自律的学習者へ導くことを目指している。また、ただ単に学問的な専門知識を授けるだけでなく、それを応用する力を伸ばすことを目指し、教育方法の工夫を重ねている。
|
|
2.
|
【研究活動の方針】 「企業の社会的責任」という言葉が定着してきた。企業だからと言って、利益のためなら何をしても良いわけではない。しかし、経済は企業だけで成り立っているのではない。消費者の呼応があって初めて成立する。それなのに、経済活動に伴う弊害の責任を企業だけに負わせて良いのだろうか。このような信条から、どのように働きかけたら消費者の選択を変え、社会を変えることができるか?を研究している。
|
|
3.
|
【社会貢献活動の方針】 研究活動の過程で得た知見を実社会に還元する。また、教育活動と社会貢献活動をリンクさせる。さらに、社会貢献活動を通じて見つけた疑問を新たな研究課題とすることで、教育活動、研究活動、社会貢献活動の三つを相互に連関させることを目指している。
|
|
■ メールアドレス
|